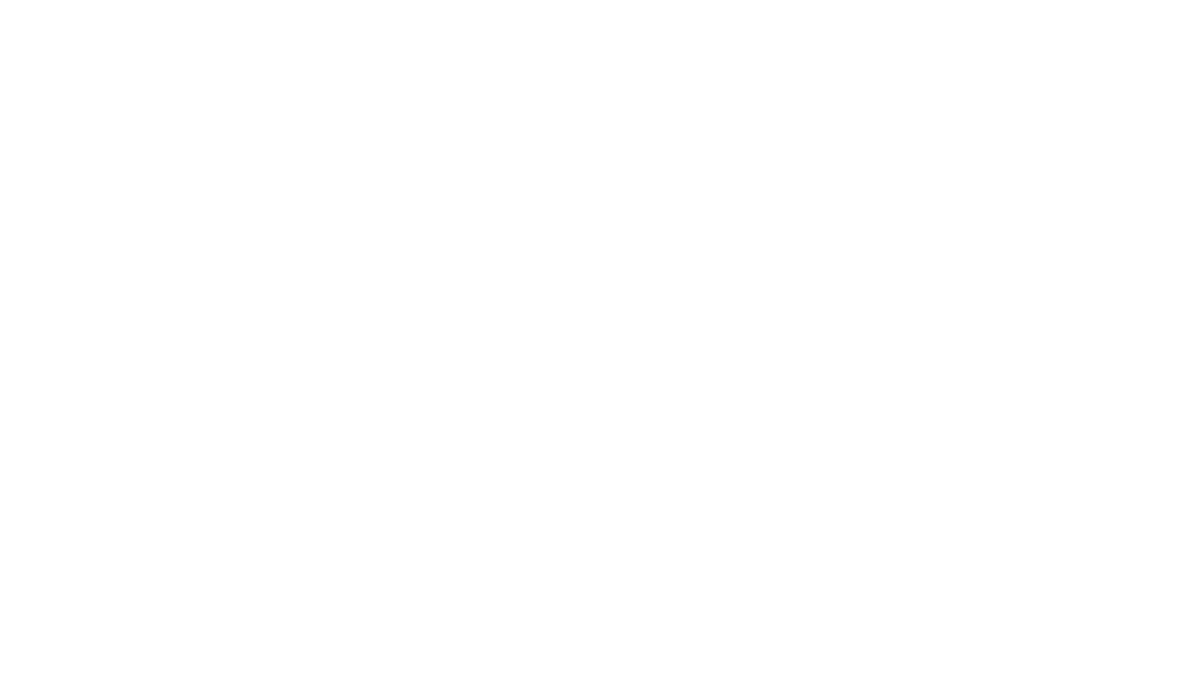こんにちは、がねです。北向きの平屋(北西角地で、南東側には隣家がある)に住み始めて来月で丸2年が経ちます。
10ヶ月ほど前、「北向きの家に住んで1年。リビングは暗い?後悔した?」という記事を投稿しました。
内容としては
- 直射日光は入らないけど、1日中一定の明るさを保っていますよ
- 北側の眺望は最高ですよ
- 冬は暗くて寒いけど夏は最高ですよ
- 大きな後悔はしていないが、数年後にはどう感じているか分からないですよ
こんな感じでした。今読んでみると我ながら全く参考にならない記事だなぁ、と思います。(笑)
あれから約10ヶ月。
正直、リフォームしたいです。(はやっ!)
冬、寒すぎます、暗すぎます、鬱々します。(笑)
北向きの家、暗くて寒い。失敗した原因【住んで2年】

天気の悪い日に撮影した上の写真ですが、見るだけでどんより暗く、吸い込まれていきそうになりますよね。(笑)このグレーのクロスが暗い原因でもあるのですが。
なぜ北向きにした?
まず大前提として、北向きにしたことは後悔していません。この土地を購入した決め手が北側の眺望だったためです。(たくさんの選択肢の中から進んでここに決めたというより、予算的に買えるのがここぐらいしかなかった)
北西角地の場合、大抵は建物を北側ギリギリに寄せてできるだけ南側隣家との距離をとった設計にすると思うのですが・・
我が家はその真逆なんですよね。(笑)
南側に建物を寄せて北側を広くとって、ドッグランにしています。(と言っても、狭い庭ですが)
なぜかというと、北側の開けた景色を眺められるリビングにしたかったからです。
庭が北側にあるので、隣家を気にせず犬を遊ばせることができます。もしまたこの土地で建て直すことができたとしても、北向きにします。
耐えられないこと
ただ一つ耐えられないのが、冬の時期の寒さと暗さです。
2019年12月に入居して、1回目の冬はマイホームハイで特に何も感じていなかったと思います。2回目の冬(前回の記事を投稿した時)は、後悔まではしていないけど、ちょっと危ない状態。(笑)
そして、3回目の冬・・「あ、ダメだ、鬱々する。」と、もう自分の気持ちをごまかせなくなりました。(笑)
というより今年の3月~4月辺りから、『外は暖かいのに家は影になっていて直射日光も入らず寒い・・』という状態でかなり鬱々していました。この家が快適なのは6月~9月の夏だけです。(笑)
失敗の原因
失敗の原因と言っていいのか分かりませんが、家が暗い件で選択ミスだったなと感じる点が2つあります。
一つ目は、南東に建つ隣家を気にしすぎて窓を減らしてしまったことです。採光よりも隣家への騒音・視線対策を優先しすぎて、南東側の窓を極端に減らしすぎました。
二つ目は、南側からの採光は高窓1つで十分だろうと甘く見積もっていたことです。

そう考えるに至った要因はあってですね・・。
以前住んでいた賃貸アパートが南西向きで、直射日光がガンガンに入ってくる部屋でした。あまりにも明るすぎる部屋で、頭痛の原因になっていました。直射日光に対する拒否反応が生まれて「新しい家は明るすぎない家にしたい」と思うようになったんですよね。
(冷静に考えれば、そもそも以前の日当たり良すぎるアパートと今の土地では立地条件が違うわけで、比べるのはおかしいだろという話なんですが。)
そんなこんなで南側からの日光があまり入らない家になってしまい。冬が暗すぎ寒すぎでメンタルに影響を及ぼすという、自業自得な結果となったのです。
寒さに関して
ただ、家が寒い問題に関しては、断熱材やサッシの工夫でどうにかなったのかなとも思います。
断熱材・・グラスウール
サッシ・・アルミ樹脂複合サッシ(リクシルのサーモスⅡH)
北側に掃き出し窓
日当たりが悪いうえにこんな条件の家だったらそりゃあ寒いですよね。
まぁ、的外れな素人考えなのかもしれないのですが・・
おわり
北向きの家でも、しっかり設計・対策していれば快適な家づくりはできるのだと思います。
もっと知識をつけて、設計士さんともしっかり話をしておくべきでした。
今後はリフォームも視野に入れて考えていくつもりです。
では!読んでいただきありがとうございました。